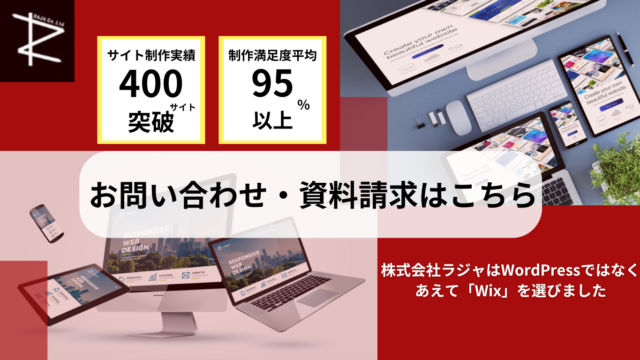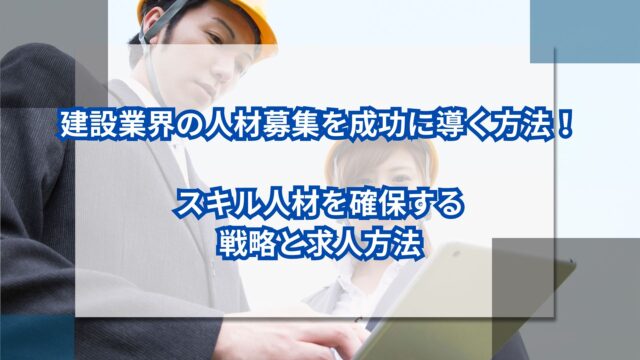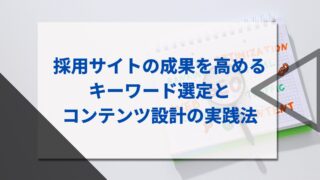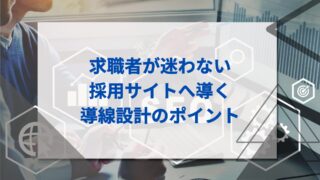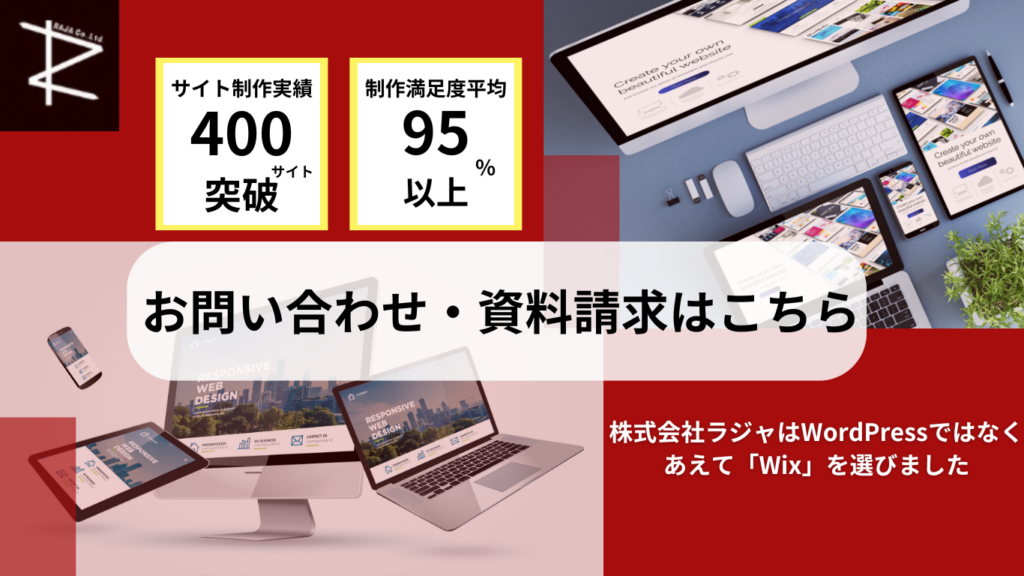人材採用にかかるコストが年々上昇し、「もっと効率よく、安く採用できないか?」と悩む企業様は少なくありません。求人広告費や面接にかかる時間、さらには早期離職による再採用まで含めると、想像以上に採用コストは膨らんでしまいます。
本記事では、採用活動を見直し、コストを効果的に削減する具体的な方法を、中小企業向けにわかりやすく解説します。
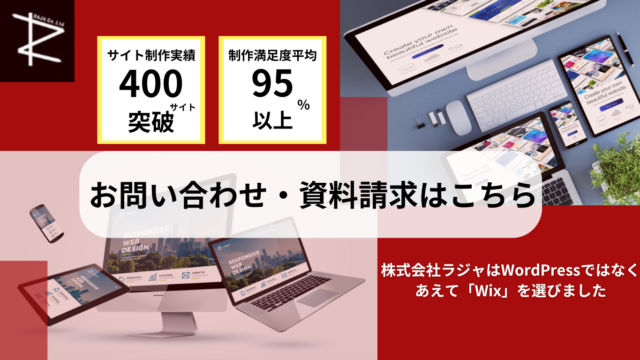
採用コストとは?まず知っておきたい基礎知識

採用コストの定義と内訳
採用コストとは、人材を採用するために企業が支出するすべての費用を指します。表面的な求人広告費や人材紹介料だけでなく、人事部門の業務にかかる時間や、面接に関わる交通費、採用後の研修費用も含まれます。多くの企業では、これらを「外部コスト」と「内部コスト」に分けて管理しています。
一般的に採用活動には目に見えないコストも多く、実際には「想定以上に費用がかかっていた」と後から気づくケースも少なくありません。採用戦略を見直す際には、この採用コストの構造を理解することが不可欠です。
内部コストと外部コストの違い
採用コストは大きく分けて「内部コスト」と「外部コスト」に分類されます。
- 内部コスト:人事担当者の人件費、面接調整や書類選考にかかる工数、研修費など、企業内部で発生するコスト
- 外部コスト:求人媒体への掲載料、人材紹介会社への手数料、合同説明会出展費、採用イベント運営費など、社外に支払う費用
この2つを区別することで、どこに無駄があるのかを可視化しやすくなります。採用活動の効率化や費用削減を考える際は、それぞれのコストを分解して見直す視点が重要です。
採用単価の計算方法
採用単価とは、1人の人材を採用するのにかかった総費用を意味し、採用活動の費用対効果を測るうえで重要な指標です。計算式はシンプルで、
採用単価=総採用コスト ÷ 採用人数
たとえば、年間300万円の採用費用で10人を採用した場合、採用単価は30万円となります。この指標を年ごとに比較することで、採用手法の見直しや最適化の効果を測定することができます。
ただし注意点として、早期離職者を含めて計算してしまうと、採用の成果が正確に測れなくなるため、集計対象の定義は社内で統一する必要があります。
なぜ採用コストを削減する必要があるのか
採用活動に予算をかけること自体は悪いことではありませんが、成果に見合わない支出が続けば、企業経営にとっては大きな負担となります。特に中小企業では、採用失敗による再募集が財務に与える影響は大きく、1回のミスマッチが年間予算を圧迫することもあります。
さらに、採用費を必要以上にかけすぎると、他の人事施策や人材育成への投資が難しくなるという副作用も生まれます。そのため、採用コストを適切にコントロールすることは、経営の健全性を保つうえでも非常に重要なのです。
採用コストを削減する具体的な方法

採用コストの内訳が明らかになったら、次は「何をどう改善すべきか」という実践的な段階に進みます。ここでは、実際に多くの企業で導入されている削減手法を紹介します。目的や社内体制に合わせて、自社に適した手段を検討することが重要です。
採用コスト削減施策マトリクス(分類×効果)
| 分類/効果 | 即効性が高い施策 | 中長期的に効果が出る施策 |
| 外部コストの削減 | ・求人媒体の見直し
・社員紹介制度(リファラル採用) |
・採用ブランディングの強化
・オウンドメディアの構築 |
| 内部コストの削減 | ・ATS(採用管理システム)の導入
・面接や説明会のオンライン化 |
・オンボーディング施策の整備
・離職防止体制の強化 |
求人媒体の見直しと選定基準
求人広告は採用コストの中でも目に見えやすい費用項目です。媒体選定が的確でないと、「応募が集まらない」「早期離職につながる」といった無駄が発生しやすくなります。
特に中小企業では、大手媒体に偏らず、地域特化型や成果報酬型サービスを利用することで、費用対効果の高い母集団形成が可能です。応募数・内定率・定着率などの数値をもとに、効果の低い媒体を段階的に削除していくことが基本です。
採用プロセスの効率化(ATS・オンライン化など)
内部コストの削減には、採用業務の見直しが不可欠です。たとえば、面接や説明会のオンライン化で移動・対応時間を削減でき、ATSの導入により、書類管理や日程調整が自動化されます。これにより人事工数の大幅な削減とスピーディーな採用実現が可能となり、コストの削減が図れます。
社員紹介制度(リファラル採用)の強化
リファラル採用は、広告費をかけずに人材を確保できる手法です。社員が信頼できる人材を推薦するため、定着率も高い傾向があります。成功にはインセンティブ設計や紹介しやすい仕組みづくりが重要で、初期費用がほとんどかからない点も魅力です。
採用ブランディングとオウンドメディアの活用
長期的な視点でコストを抑えるには、企業が自ら魅力を発信し、「選ばれる企業」になることが重要です。自社サイトやSNSを活用し、求人広告に頼らないプル型採用を確立しましょう。ノーコードツールを使えば、外注コストを抑えながら自社運用が可能です。
早期離職を防ぐオンボーディング施策
採用後の定着率が低ければ、再採用によりコストが倍増します。初日対応や1on1面談、メンター制度といったオンボーディング体制を整えることで、早期離職を防ぎ、結果的に採用コストを削減することが可能です。
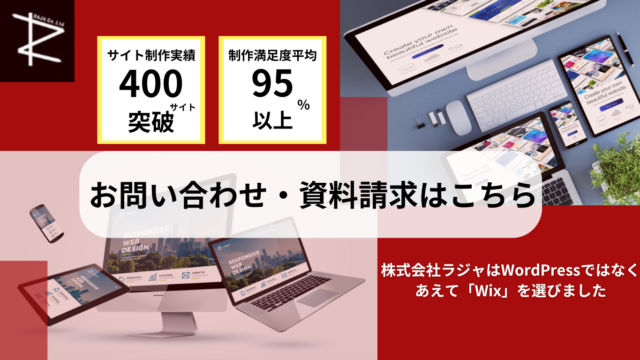
採用コストを削減するために人事ができること
採用コスト削減に向けた施策は、戦略や仕組みの導入だけでなく、人事担当者の日常業務や計画の立て方によっても大きく左右されます。ここでは、現場の人事が具体的に取り組むべきポイントを解説します。
数値目標とKPIの設定
まず重要なのが、採用活動の成果を測定するための指標(KPI)を設定することです。KPIが明確になっていないと、どの施策が有効だったのか評価できず、改善も難しくなります。
代表的なKPI例としては以下が挙げられます。
- 採用単価(1人当たりコスト)
- 応募から内定までの平均日数
- 内定辞退率・早期離職率
これらの数値は定期的にチェックし、改善のPDCAを回すことが、継続的なコスト削減には欠かせません。
人材要件の見直しと適正化
募集する人材像が曖昧なまま採用活動を進めてしまうと、ミスマッチによる早期離職や再採用が発生し、コストが倍増します。ここで必要なのが、人材要件(ペルソナ)の見直しと具体化です。
たとえば「成長意欲のある若手」ではなく、「3年以内に〇〇業務を一人称で担える、ITスキル基礎がある人」など、求める人物像を定量・定性的に具体化することがポイントです。
また、実際に活躍している社員の共通点を分析することで、要件の精度を高めることも可能です。
社内連携による採用計画の平準化
人事だけで採用活動を完結させるのではなく、各部署や経営層との連携を密にすることも重要です。特に、採用の時期や人数が年度内で偏ると、急募や短期集中採用が必要となり、コストが高騰する原因になります。
そこでおすすめなのが、次のような社内連携の仕組みです。
- 半期ごとに全社の採用計画をレビュー
- 各部門と「本当に必要な人材数」の擦り合わせを実施
- 急募が発生しないよう、リスク分散型の採用スケジュールを設定
このように、採用活動を年間を通して平準化することで、求人費や業務負荷の最適化が図れます。
外部パートナーとの連携活用
中小企業にとっては、すべてを自社内でまかなうのではなく、必要に応じて外部の専門家やツールを上手に活用することも、結果的にコスト削減に寄与します。
具体的には、次のような連携が考えられます。
- ノーコード採用サイトの導入支援(Wixなど)
- 採用管理ツール(ATS)の導入・運用代行
- 採用ブランディング支援(コンテンツ・動画制作)
導入コストを「支出」ではなく「投資」と捉え、効果検証しながら適切に使うことで、人的リソースを節約しつつ、成果の最大化が可能です。
まとめ
採用コストは「削ること」が目的ではなく、最小のコストで最大の成果を得るための最適化が本質です。本記事では、採用コストの内訳や指標を整理した上で、求人媒体の見直し、採用プロセスの効率化、社員紹介制度の活用、ブランディング、離職防止といった5つの具体策をご紹介しました。
まずは自社の採用コスト構造を可視化し、実行可能な施策から一歩ずつ取り組んでみてください。継続的にPDCAを回しながら改善を積み重ねることで、安定した人材確保と企業成長につながるはずです。